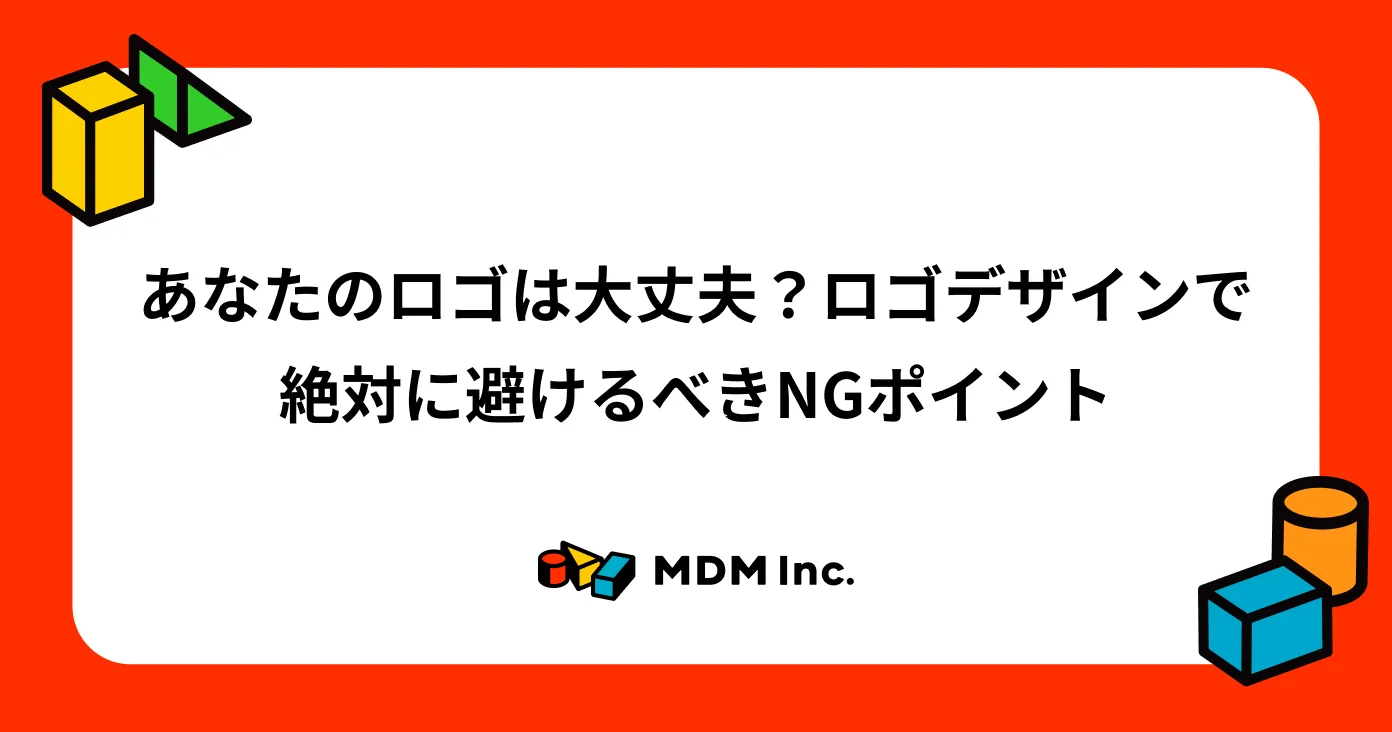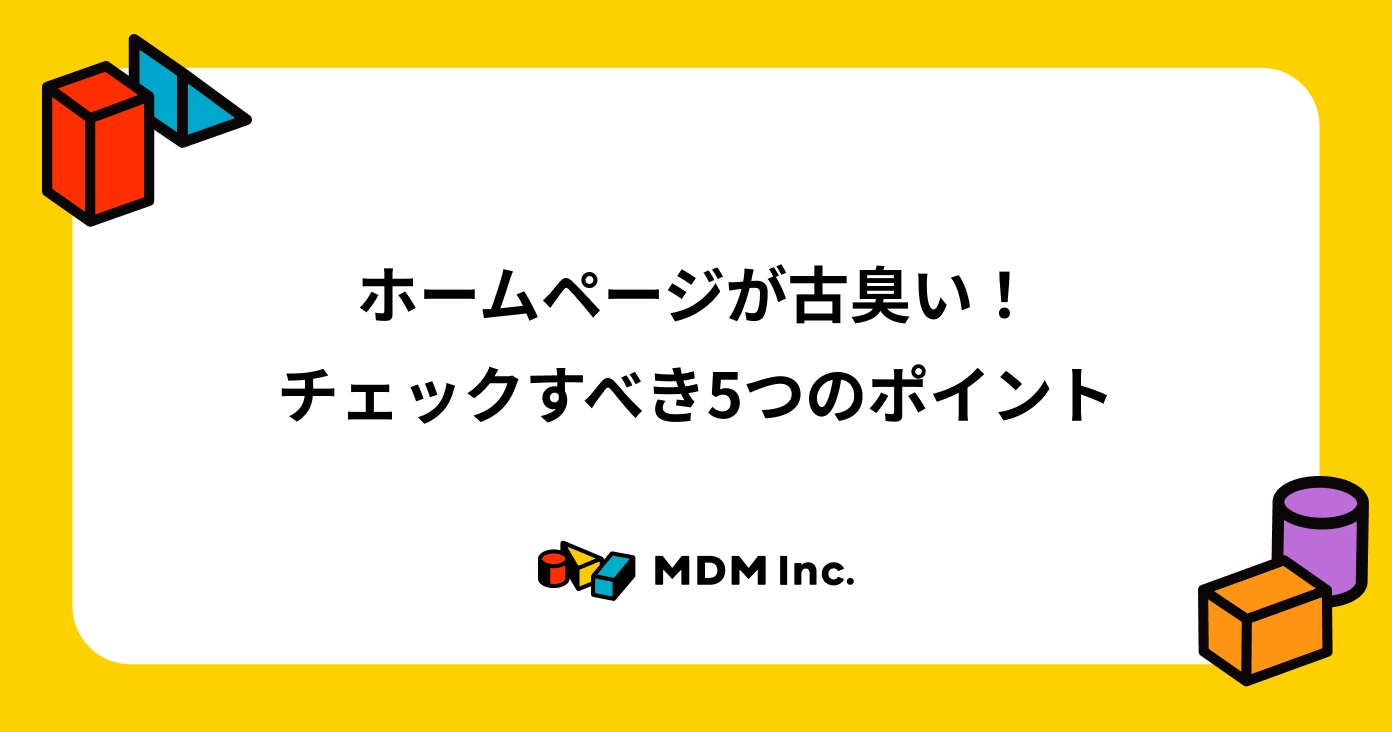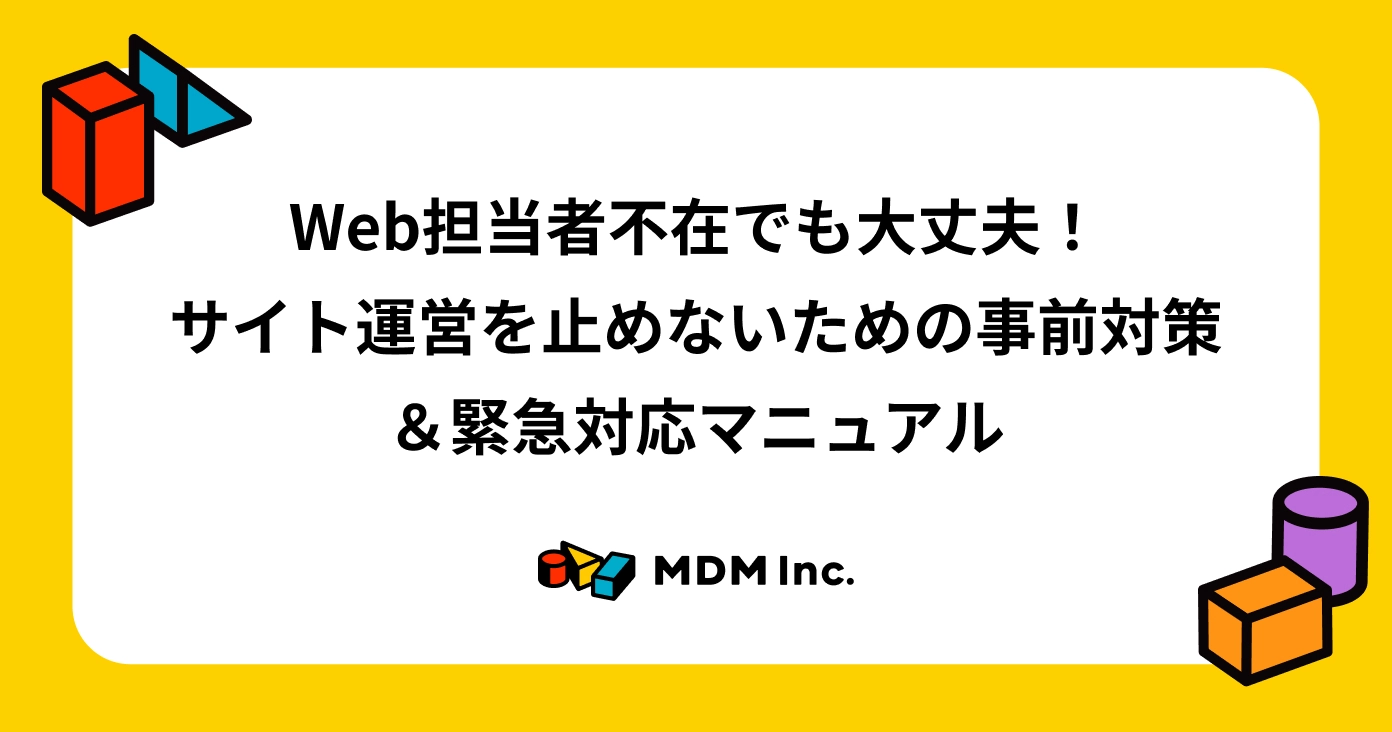ホームページは何のために?中小企業のための目的・目標設定の第一歩
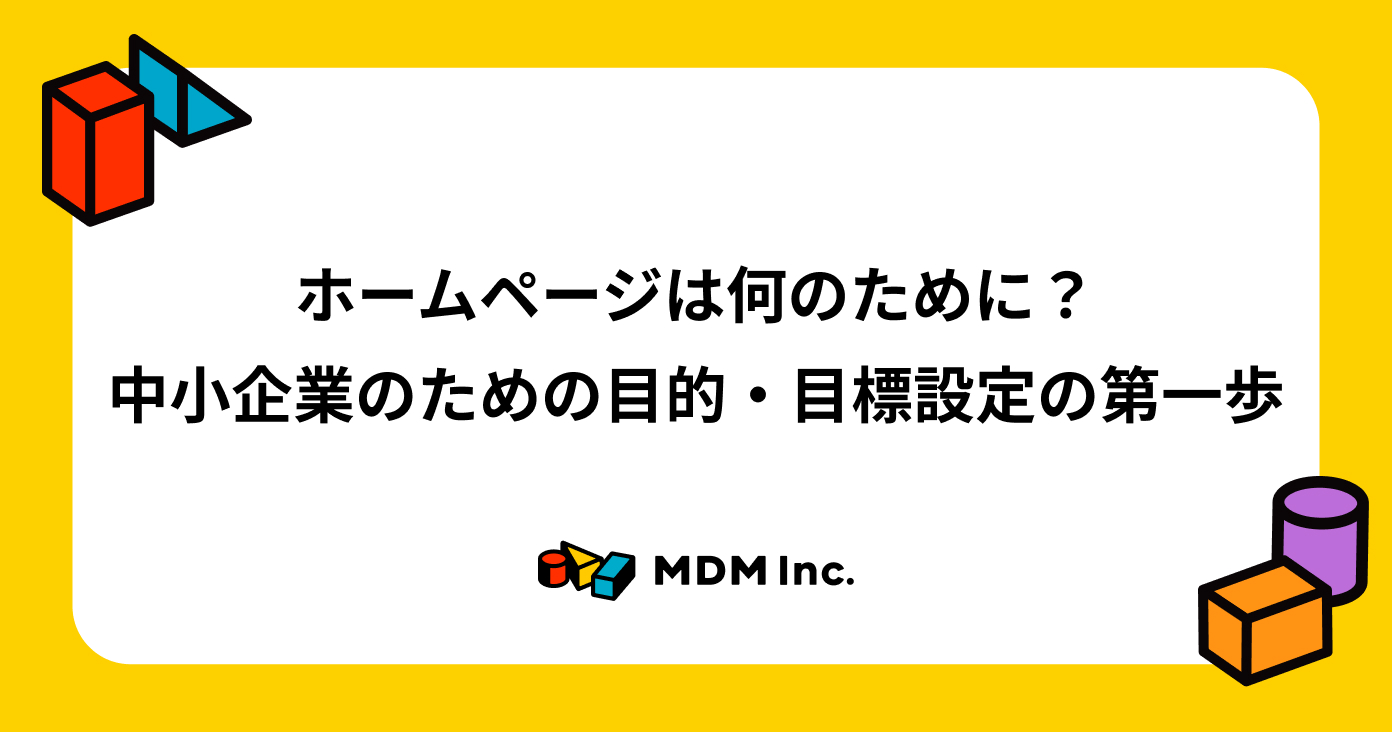
目次
はじめに:この記事を読んでわかること
あなたの会社のホームページは、元気に働いていますか?それとも、「なんとなく持っているだけ」になっていませんか?
「ホームページの目的って、結局のところ何なんだろう…?」
「目標設定と言われても、うちのホームページで何を目標にすればいいのか、モヤモヤする…」
もし、あなたがそんな風に感じているとしたら、このブログ記事はきっとお役に立てるはずです。特に、日々の業務に追われ、ホームページのことまで手が回らないと感じている中小企業の経営者様やご担当者様に向けて、分かりやすく解説していきます。
この記事では、あなたの会社のホームページがなぜ存在するのか、その「存在意義」をしっかりと見つけ出すためのステップを、専門用語を使わずに丁寧にご説明します。
この記事を最後まで読むことで、あなたは以下のことを知ることができます。
- 多くの会社がなぜ「なんとなく」ホームページを作ってしまうのか、その落とし穴
- ホームページを持つことで実現できる3つの基本的な目的
- 誰に情報を届けたいのか、「ターゲット顧客」を具体的にイメージする方法
- 目的とターゲットが決まれば、ホームページでどんな情報を伝え、どんな行動を促すべきかが明確になること
ホームページは、目的をハッキリさせれば、会社の強い味方になります。さあ、一緒にあなたの会社のホームページの「存在意義」を見つけに行きましょう。
あなたの会社のホームページ、”なんとなく”作っていませんか?
多くの会社が陥る「なんとなく」ホームページ
「ホームページ? ああ、うちも一応持ってるよ。」
中小企業の経営者様やご担当者様と話していると、こんな言葉をよく耳にします。名刺にもホームページのアドレスが載っているし、会社案内にも記載している。なんとなく、「持っているのが当たり前だから」作ってみた。もしくは、付き合いのある制作会社に勧められて作った。
でも、正直なところ、「このホームページで何をしたいのか?」と聞かれると、返答に詰まってしまう…。そう感じている方も少なくないのではないでしょうか。多くの会社が、特別な目的意識を持たずに、”なんとなく”ホームページを運用しているのが実情かもしれません。
目的がないと、どうなる?(時間とお金の無駄遣い?)
“なんとなく”で作られたホームページは、残念ながら、会社の役に立つことが少ないです。
例えば、会社やサービスの情報は載っているけれど、それが「誰に」「何を伝えたいのか」がハッキリしない。お問い合わせフォームはあるけれど、どこにあるか分かりにくい。お知らせは古い情報のまま何年も更新されていない…。
これでは、せっかく時間やお金をかけて作ったホームページが、ほとんど誰にも見てもらえず、会社の「資産」として活かされません。単にサーバー代や維持費だけがかかる、お荷物になってしまう可能性もあります。これは、非常にもったいないですよね。
じゃあ、どうすればいいの?まずは立ち止まって考えてみよう
では、どうすれば、ホームページを会社の役に立つ「使える資産」に変えられるのでしょうか?
答えはシンプルです。「何のためにホームページを持つの?」という一番大切な問いに、しっかりと向き合うことです。
急に「目的を決めましょう!」と言われても、ピンとこないかもしれません。大丈夫です。まずは難しく考えず、「今あるホームページは、何のためにあるんだろう?」「これから作るホームページは、何のために使いたいんだろう?」と、少しだけ時間を取って立ち止まり、考えてみましょう。この「立ち止まって考える」という行動こそが、ホームページを生まれ変わらせるための、最初の一歩になります。
なぜホームページを持つのか?3つの基本パターン
ホームページを持つ目的は、会社の数だけある、と言えるかもしれません。ですが、多くの会社の目的をシンプルに分けると、だいたい次の3つのパターンのどれかに当てはまることが多いです。もちろん、複数の目的を組み合わせることも可能です。
パターン1:会社や事業を知ってもらうため(名刺代わり・情報発信)
これは、多くの会社にとって、ホームページを持つ一番最初の目的かもしれません。インターネット上に会社の「顔」となる場所を作り、「私たちはこんな会社で、こんな事業をやっていますよ」と知ってもらうためのパターンです。
たとえるなら、立派な会社案内や名刺をオンライン上に置くイメージです。会社の沿革や事業内容、所在地、連絡先などを掲載し、会社の信用度を高めたり、取引先候補に安心感を与えたりする役割があります。
このパターンが向いているのは…
- まずは会社の存在を広く認知してもらいたいと考えている会社
- 既存顧客や取引先に対して、会社の最新情報などを定期的に発信したい会社
- 採用活動において、会社の雰囲気を伝えたいと考えている会社
パターン2:問い合わせや資料請求を増やすため(集客装置)
これは、ホームページを「会社の利益につながるお客様を見つける道具」として積極的に活用したい場合の目的です。ホームページを見てくれた人に、「もっと詳しく知りたい」「見積もりをお願いしたい」と思ってもらい、問い合わせや資料請求といった具体的な行動を促すことを目指します。
あたかも、インターネット上に強力な営業担当者を置くようなものです。サービスの詳細や導入事例、お客様の声などを掲載し、見込み顧客の疑問や不安を解消し、信頼を得て、最終的な受注につなげるための入り口とします。
このパターンが向いているのは…
- 新規顧客からの問い合わせを増やしたいと考えている会社
- 特定のサービスや商品への資料請求を増やしたい会社
- インターネット経由での売上アップを目指したい会社
パターン3:採用活動を成功させるため(人材獲得)
近年、特に重要視されている目的の一つです。会社の理念や働く環境、先輩社員の声などを詳しく掲載し、自社で活躍してくれる新しい人材に出会うためのツールとしてホームページを活用します。
求人サイトの情報だけでは伝えきれない、会社の雰囲気や文化を伝えることで、自社に合った意欲的な人材からの応募を増やし、採用のミスマッチを減らす効果が期待できます。
このパターンが向いているのは…
- 会社の成長のために、優秀な人材を積極的に採用したい会社
- 会社の魅力や働く環境を求職者にしっかりと伝えたい会社
- 採用コストを抑えつつ、効果的な採用活動を行いたい会社
複数の目的があっても大丈夫!優先順位をつけよう
ここまで3つのパターンをご紹介しましたが、「うちの会社は、知ってもらいたいし、問い合わせも増やしたいし、採用にも使いたいんだよな…」と思われたかもしれません。もちろん、複数の目的を持っていても全く問題ありません!
むしろ、一つのホームページが複数の役割を担うことはよくあります。ただし、欲張ってあれもこれもと詰め込みすぎると、結局何が一番伝えたいのかが分かりにくくなってしまうこともあります。
まずは、この3つのパターンの中で、「今、一番力を入れたいことは何か?」という視点で、優先順位をつけてみるのがおすすめです。優先順位が決まると、ホームページで何を一番目立たせるべきか、どんな情報を充実させるべきかが見えてきます。
「誰に」届けたい?ターゲット顧客を具体的にイメージしよう
ホームページの目的が「会社を知ってもらう」「問い合わせを増やす」「採用を成功させる」など、何となく見えてきたでしょうか。目的の次に考えるべき、非常に大切なことがあります。それは、「一体誰に、その目的を達成するための情報を見てほしいのか?」ということです。つまり、ホームページの「ターゲット顧客」を明確にすることです。
なぜ「誰に」が大切なの?(みんな、は誰でもない)
「うちは、どんなお客さんでも大歓迎だから、ターゲットは『みんな』だよ!」
そう思われる社長さんや担当者の方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、たくさんのお客様に来ていただくことは素晴らしいです。しかし、ホームページを作る上で「ターゲットはみんな」としてしまうと、結果的に「誰にも響かない」ホームページになってしまうことが多いのです。
考えてみてください。「みんな」に向けて話そうとすると、どうしても当たり障りのない、一般的な話になってしまいますよね。でも、特定の人に話しかけるときはどうでしょう? その人の趣味や関心に合わせた、具体的な話ができますよね。
ホームページも同じです。「みんな」に向けて作られたホームページは、情報が漠然としていて、「これは自分のために書かれた情報だ!」と強く感じてもらいにくいのです。逆に、「あ、この会社は私たちのことを分かってくれているな」と感じてもらうには、「誰に」向けて書くのかをハッキリさせることが不可欠です。
具体的なターゲット顧客像の描き方(ペルソナの簡単な考え方)
では、「誰に」を具体的にするにはどうすれば良いでしょうか? 難しく考える必要はありません。あなたの会社にとって、「理想のお客様」はどんな人かを具体的にイメージしてみることから始めましょう。マーケティングの世界では、こうした理想のお客様像を「ペルソナ」と呼んだりしますが、まずは固有名詞を覚える必要はありません。
例えば、
- どんな業種・業界の会社ですか? (例:製造業、IT企業、建設業など)
- 会社の規模はどのくらいですか? (例:従業員〇〇人以下、売上〇〇円くらい)
- ホームページを見てほしい担当者の役職は? (例:購買部の部長、情報システム部の担当者、総務部の課長など)
- その担当者は、どんなことに悩んでいそうですか? (例:コスト削減、業務効率化、人材不足、新しい技術の導入など)
- どんな情報を求めていそうですか? (例:成功事例、価格情報、製品の比較、導入までの流れなど)
このように、一人の人物になりきったつもりで、具体的な人物像を想像してみましょう。実際に、社内の営業担当者の方などに聞いてみるのも良い方法です。一番多くお付き合いのあるお客様や、今後こんなお客様と取引したいというお客様を具体的に思い浮かべてみるのがおすすめです。
ターゲット顧客の悩みや知りたいことは何?
ターゲット顧客の人物像が見えてきたら、次に考えたいのが、「そのターゲット顧客は、ホームページで何を知りたいのだろう?」「どんな悩みを解決したいと思って、私たちの会社のホームページにたどり着くのだろう?」という視点です。
例えば、もしターゲット顧客が「コスト削減」に悩む製造業の購買部部長だとします。その方は、ホームページでどんな情報を探すでしょうか?
- 製品・サービスを導入することで、具体的にどれくらいコストが削減できるのか?
- 他の製造業の会社で導入に成功した事例はあるのか?
- 初期費用やランニングコストはどのくらいかかるのか?
- 導入のハードルは高くないのか?
このように、ターゲット顧客の立場になって考えてみると、ホームページに載せるべき情報や、どんな言葉遣いが響くのかが見えてきます。ホームページは、あなたの会社が伝えたい情報だけを載せる場所ではなく、ターゲット顧客が知りたい情報を提供する場所だと考えると、より効果的なホームページに近づけるはずです。
ターゲットが決まれば、ホームページの役割も見えてくる
ここまでで、あなたの会社のホームページの「目的」と「誰に届けたいか」という「ターゲット顧客」が少しずつ見えてきたと思います。この二つが明確になると、ホームページが具体的にどんな「役割」を担うべきなのか、ぐっと分かりやすくなってきます。
ターゲット顧客に合わせたコンテンツの考え方
ホームページの「コンテンツ」とは、そこに載っている情報すべてを指します。文章、写真、動画、図、お客様の声、事例紹介など、すべてがコンテンツです。
ホームページの目的が「問い合わせを増やす」で、ターゲット顧客が「コスト削減に悩む製造業の購買部部長」だったとしましょう。この場合、ホームページに載せるべきコンテンツはどんなものが考えられるでしょうか?
- コスト削減の具体的な方法についての役立つ情報
- ターゲット顧客と同じような製造業での成功事例(数字入りだと説得力が増します)
- 導入することで削減できるコストのシミュレーションや具体的なメリットの説明
- 製品やサービスの価格体系について分かりやすく説明したページ
- よくある質問とその回答(FAQ)で、ターゲットが抱えるであろう疑問を先回りして解消
このように、ターゲット顧客が「知りたいこと」や「悩みの解決につながること」を中心にコンテンツを考えていくと、自然とホームページに載せるべき情報が見えてきます。逆に、ターゲットが全く興味を持たないような、会社側の都合だけの情報をたくさん載せても、読んでもらえません。
ターゲット顧客が「ほう、この情報、役に立つな」「もっと詳しく知りたいな」と感じるような、価値のあるコンテンツを用意することが大切です。
ホームページで実現したい「具体的な行動」を考えよう(問い合わせボタン、資料ダウンロードなど)
ターゲット顧客がホームページを訪れて、求めている情報を見つけたとします。次に、そのターゲットにホームページ上でどんな「具体的な行動」を取ってほしいでしょうか? これを明確にしておくことも、ホームページを成功させるためには非常に重要です。
ホームページの目的によって、取ってほしい行動は変わります。
- 目的:会社や事業を知ってもらう → 会社概要ページを見る、事業紹介ページを見る、IR情報を見る
- 目的:問い合わせや資料請求を増やす → 問い合わせフォームから連絡する、資料ダウンロードをする、デモを申し込む、電話をかける
- 目的:採用活動を成功させる → 採用情報ページを見る、社員インタビューを読む、エントリーする
これらの「具体的な行動」を、ホームページ上で分かりやすく誘導する必要があります。例えば、問い合わせを増やしたいなら、各ページの分かりやすい場所に「お問い合わせはこちら」というボタンを設置したり、資料ダウンロードの案内を目立たせたりすることが大切です。
この、ターゲットに取ってほしい具体的な行動のことを、「コンバージョン」と呼んだりもしますが、難しく考えず、「ホームページを見に来てくれた人に、最後にどうなってほしいか?」を考えてみてください。そして、その行動を促すための仕掛けをホームページに準備しましょう。
成功している会社の事例を見てみよう(簡単な紹介)
もし可能であれば、あなたの会社のターゲット顧客に近いお客様を持つ、成功している他社のホームページを見てみるのも非常に参考になります。
彼らのホームページは、どんなターゲットに向けて、どんな情報を、どのように見せているでしょうか? どんなコンテンツが用意されていて、どのように「問い合わせ」や「資料請求」といった次の行動に誘導しているでしょうか?
例えば、とあるBtoBの製造業の会社では、ターゲットである「現場の技術者」に向けて、専門的な製品情報を分かりやすい動画で解説したり、製品導入後の具体的な効果を数値で示したりするコンテンツを充実させた結果、技術者からの問い合わせが大幅に増加したという事例があります。彼らは、ターゲットが知りたい情報を、ターゲットにとって最も理解しやすい方法で提供したのです。
他の成功事例から学ぶことはたくさんあります。ぜひ、ターゲット顧客がどんな情報を求めているかのヒントを得るために、色々な会社のホームページを参考にしてみてください。
まとめ:目的意識がホームページ成功の第一歩
今日の振り返り
今日は、あなたの会社のホームページが「なんとなく」存在する状態から脱却し、「我が社の存在意義」を見つけるための大切なステップについてお話ししてきました。少し内容を振り返ってみましょう。
- まず、あなたの会社のホームページが、「何のためにあるのか?」という目的を立ち止まって考えることの重要性をお伝えしました。「なんとなく」では、時間もお金も無駄になってしまう可能性があるからです。
- 次に、ホームページを持つ3つの基本的な目的パターンをご紹介しました。「会社を知ってもらう(情報発信)」「問い合わせを増やす(集客)」「採用を成功させる(人材獲得)」といったパターンから、貴社の状況に合った目的を考えるヒントを得られたかと思います。
- そして、その目的を達成するために、「誰に」情報やメッセージを届けたいのか、つまり「ターゲット顧客」を具体的にイメージすることの大切さをお話ししました。「みんな」ではなく、特定の「理想のお客様」を思い描くことで、響くメッセージが生まれます。
- 最後に、目的とターゲットが明確になれば、ホームページにどんな情報を載せるべきか(コンテンツ)、そしてターゲットにどんな行動を促すべきかが明確になることお伝えしました。
ホームページは、単なる会社情報が載っているだけの場所ではありません。明確な目的とターゲットがあってこそ、会社のビジネスに貢献してくれる強力なツールになり得ます。
次の一歩を踏み出しましょう
今日の話を読んで、「よし、うちのホームページの目的、改めて考えてみようかな」「ターゲット顧客って、もっと具体的にイメージできるかもしれないな」と感じていただけたら、これほど嬉しいことはありません。
難しく考える必要はありません。まずは、この記事を読みながら考えたことを、社内の担当者や経営者仲間と話し合ってみることから始めてみてはいかがでしょうか。
- うちの会社のホームページ、一番の目的って何だろう?
- 一番来てほしいお客様って、どんな人だろう?
- そのお客様は、うちのホームページで何を知りたいと思うだろう?
こんな簡単な問いからでも良いのです。ホームページの目的意識を持つことは、ホームページを成功させるための、そして会社のビジネスをさらに発展させるための、間違いなく第一歩となります。
もし、今お持ちのホームページが今日の話と少しずれているな、と感じたとしても大丈夫です。これからのホームページ運用に、今日の考え方を取り入れていけば良いのです。これからホームページを作るという方は、ぜひ今回のステップを踏まえて企画を進めてみてください。
あなたの会社のホームページが、明確な「存在意義」を持ち、ビジネスの力強い味方になることを心から応援しています!